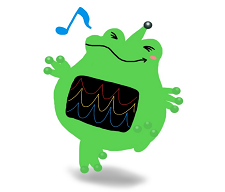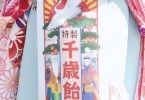最近は、この時期の週末や祝日に分散して行われている七五三ですが、ちょっと昔は11月15日が定番の行事のように言われていました。
少子化の進む昨今、子どもの行事には、両親のみならずおじいちゃんおばあちゃんも総出で繰り出してお祝いすることも珍しくなく、家族の都合等すり合わせて日取りを選ぶために、期間の幅が広くなっていくのも自然な流れなのでしょう。
それでも、できれば11月15日に近い日程にしたほうがいいのでしょうか?この日にはどんないわれがあるのでしょう。
江戸時代に定着した七五三の形式
七五三のお祝いの形は、微妙に地域差があります
現在「七五三」は、子どものそれまでの成長を祝い、これからの更なる健やかな成長を祈願するために行う行事になっています。
子どもに晴れ着を着せて、写真屋さんで写真を撮ったり、ご馳走を食べたりして祝うのが、一般的な感じです。
関東では、昭和の頃は参詣とご祈祷が定番でした。
今も、首都圏では神社やお寺にお参りする家族が多く、特別に玉串料(お寺の場合は御布施)を払ってご祈祷をしてもらう子どもも少なくありません。
西の方では、神事ではなく、家庭行事としてお祝いしている地域も多く、また地方によっては結婚式の披露宴のように、親戚一同や近所の人たちも集めて大きな宴会を開く慣わしの所もあります。沖縄には、七五三の風習はありません。
江戸の武家の風習が全国に広まる
7歳、5歳、3歳の子どものお祝いを揃って11月15日に行うようになったのは、江戸時代からです。
初めは将軍家を筆頭とする関東の武家の習慣でした。そこから全国へ広まったとされています。
「七五三」という呼び名で庶民にまで普及したのは明治時代になってからです。
関東から地方へ伝わるうちに、土地土地の気質や習慣に合わせて、儀式の内容やお祝いする年齢など、微妙に形が異なっていったと思われます。
江戸時代までさかのぼると、ただ祝って祈祷してもらうだけではなく、それぞれの年齢で、大人へ近づく節目となる儀式の意味も持っていました。
この儀式は、もともとは平安時代の公家のしきたりがだんだんと武家にも伝わったもので、初めは公家さんの子どもが3歳になって、初めて袴を着用する記念の祝儀(着袴[ちゃっこ]の儀)でした。
7歳・5歳・3歳 3つの通過儀礼
中世に入り、公家から武家へ伝わった子どもの通過儀礼は、時代と共にだんだん発展して、儀式の年齢や行う内容もどんどん増えていきます。
江戸時代に入る頃、武家ではこんな儀式が定番でした。他にも9歳男子や13歳女子の祝儀を行う場合もあったとか。
中国から伝わった陰陽思想の影響で、奇数は縁起がいいとされていたのです。
3歳に男女共に行う「髪置[かみおき]の儀」
疫病防止などの衛生面の配慮から、子どもは3歳までは髪を剃る習慣がありました。この儀以降、髪の毛を伸ばし始めます。
5歳の男子が行う「袴着[はかまぎ]の儀」
袴の着用のお初となる儀式です。
7歳の女子が行う「帯解[おびとき]の儀」
女児は幼児期には紐や柔らかい布が縫い付けられた着物を着たり、細い帯を撒いています。この儀以降、大人と同じ幅の帯を締め始めます。
当時は満年齢でなく、「数え歳(生まれた年が1歳、以降正月になるたびに1歳ずつ加齢)」でした。
儀式の日付は決まっておらず、その都度、家々の都合や成長ぶりを見ながら行っていたようです。
なぜ11月15日になったのか?
五代将軍徳川綱吉説
11月15日になった由来については諸説あり、最も有名なのが、「生類憐みの令」や「赤穂浪士を切腹させた将軍」として有名な徳川綱吉公が決めたとする説です。
天和元年(1681年)、綱吉公が長男の髪置の儀を11月に行おうとして、よい吉日を探した結果、暦の占いのひとつ“二十八宿”という選日法による「鬼宿日」(鬼が出歩かない日)に当たる15日が良いと決めたと言われています。
綱吉さんは、世を改革するためにいろいろな法制化を計ったことで有名な人で、ついでに袴着と帯解の儀もみんなまとめてこの日に行うことも定めました。以後、お江戸の武家社会では11月15日が恒例化していったのです。
綱吉説その2
11月15日を定めたのは綱吉ですが、実はそれ以前、3代将軍家光が孫の綱吉(幼名は徳松)の袴着の儀に、病弱だった徳松を案じて特に吉日として選んだ日が11月15日だったという説もあります。
家光は綱吉と違って家臣からも人民からも人気のある公方様だったので、家来たちもこれに習って11月15日に行うようになっていったと言われています。
霜月祭説
11月15日が慣習化していた理由としては、家光以前からの傾向を説くものもあります。
旧暦の11月は今より1か月ほど遅い時期で、冬至に近い頃です。秋の収穫ももうすっかり終わった後で、農村では一年の実りを神様に感謝する月であり、都市部では家業の神様を祀って感謝を捧げる「霜月祭」が15日に行われていました。
そのついでに子どもへの加護も祈願するようになった、という説です。(霜月祭は今も新嘗祭[にいなめさい]という宮中の収穫祭行事として、毎年11月23日に行われています)
日取りを決めるのは、家族と神社仏閣と写真館の都合
日程は家族の都合で選びましょう
まあ、諸説ありますが、特に宗教的な意味があるというよりも、人間の都合や暦の吉兆で決まった日のようです。大事なのは、やはり子どもの成長を祝い・願う気持ちですから、現在の私たちは、無理して11月15日にこだわらなくてもよい感じです。
ただし、神社やお寺での祈祷を希望する家族の場合は、時期によっては受け付けてくれない所もありますから、どうしてもこの時期に集中してしまうのは仕方ないですね。
また、超人気の写真屋さんでの撮影をメインイベントと考える人は、予約状況によってはうんと早い時期にやったり、12月以降まで順番を待たされたりすることもあるようです。
人気の神社のお土産が欲しい人はできるだけ空いている日に
最近は、首都圏でも祈祷をしないで普通にお賽銭を入れてお参りするだけで参詣を済ませる親子が増えているそうです。神社仏閣としては、ただでさえ少子化なご時世ですから、顧客確保のためいろいろサービスを充実させる所も出てきています。
有名な所では、もちろん玉串料もそれなりに取るのでしょうが、千歳飴と有難いお札と玩具までお土産につけてくれる所もあります。そんな人気神社狙いの人たちは、できるだけ混雑を避けた日程を調整する努力をしているようです。
かわいい子どものお祝いですから、周りはいろいろ熱くなることもあるでしょう。
一生に一度の記念だからといって、親があまり張り切り過ぎて、遠くの有名な神社や写真館に予約したものの、着慣れない着物に思いの外苦労する子どもが、長い移動に疲弊してしまうこともあるようです。
日程も着物の格も神社や写真屋さん選びも、親の自己満足にならないよう、子どもにとって一番いいことを選んであげると、結局、おじちゃんおばあちゃんの都合の良い日に、近所の氏神様にお参りして、レストランにてみんなでお食事、というパターンに落ち着く家族が多いのかもしれません。
一番大事なのは、「子どもの成長を祝い・願う気持ち」だから、無理して11月15日にこだわらなくてもいいんだね!
まさケロンは人気神社のお土産がほしいから、混雑を避けた日程を狙っていくよ!